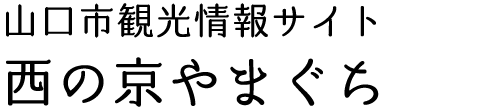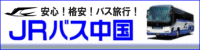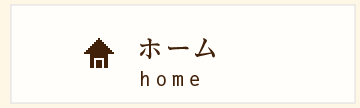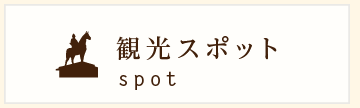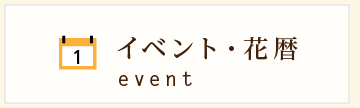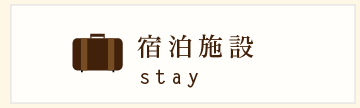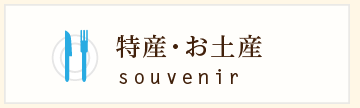地域 » 徳地エリア カテゴリー » 観光スポット(神社・仏閣・聖堂)
三坂神社 〈弾除け神社〉(みさかじんじゃ・たまよけじんじゃ)

三坂神社は古くは御坂宮(御坂神社)と称し、『東大寺正倉院文書』にも登場する古社(延喜式内社)です。古来、この世とあの世の境界(黄泉比良坂)の守護神、災難を除ける「いのち」の守護神として信仰を集めました。
中世以降、武運長久の神として有名になり、足利尊氏、豊臣秀吉、藩主・毛利家を始め、歴代武将らの厚い崇敬を受けました。戦時中、「日清・日露戦争の際、三坂神社に祈願して出征した兵士全員が生還した」と報道されると、「弾除け神社」として知られるようになりました。「強運の神様」の加護を求め、全国各地から祈願に訪れた家族らは、出征軍人の写真を奉納しました。その数は2万5千枚にものぼります。
境内には「歴史館」があり、神社の史料や出征軍人の写真を見学できます。
史跡 「御能原」
室町幕府の初代将軍となる足利尊氏は「建武の乱」の頃、九州へ落ち延びる途上、三坂神社に滞在して武運を祈願しました。尊氏は神社の裏手で自ら能楽を舞い、三坂大神に奉納したと伝えられます。そのために、三坂神社の裏手に「御能原」という地名が付いたのです。